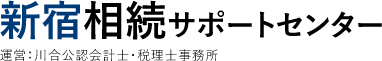相続税の負担を軽減!小規模宅地等の特例の適用要件とは?
相続税は、相続財産の総額に応じて課される税金ですが、その負担は決して軽いものではありません。
「小規模宅地等の特例」は、土地の評価額を最大80%減額できるため、節税効果の高い制度といえます。
今回は、この特例の概要や適用要件について解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例は、条件を満たす宅地等(土地または土地の上に存する権利)の評価額を大幅に減額し、相続税を軽減する制度です。
例えば、居住用宅地なら最大80%の評価減が認められ、大きな節税効果が期待できます。
適用対象となる宅地等と適用要件
特例が適用される宅地等には、以下の3つの区分があります。
それぞれの要件を解説していきます。
1. 居住用の宅地(特定居住用宅地等)
被相続人や同一生計の親族が居住していた宅地等が対象です。
評価減の割合は最大80%、適用面積の上限は330㎡です。
対象者は主に配偶者や同居親族ですが、親族の場合は、相続開始直前から申告期限までその建物に居住し、土地を保有している必要があります。
一方、配偶者には制限がありません。
2. 事業用の宅地(特定事業用宅地等)
被相続人や同一生計の親族が事業を営んでいた宅地等が対象で、評価減の割合は最大80%、適用面積の上限は400㎡です。
相続人が申告期限まで事業を継続し、土地を保有していることが条件です。
特定同族会社の事業用宅地等では、相続人が法人の役員であることも要件となります。
ただし、原則として、相続開始前3年以内に新たに利用された土地は対象外です。
3. 貸付事業用の宅地(貸付事業用宅地等)
被相続人が営んでいた不動産賃貸業などの貸付事業用宅地等が対象で、評価減の割合は最大50%、適用面積の上限は200㎡です。
相続人が申告期限まで貸付事業を継続し、土地を保有している必要があります。
ただし、原則として、相続開始前3年以内に新たに貸付事業に使用された宅地等は適用外です。
必要書類の提出
特例を利用するには、相続税申告書と必要な書類を税務署に提出する必要があります。
具体的には、被相続人の居住状況や事業状況を証明する書類が求められます。
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税負担を大幅に軽減できる有効な制度です。
ただし、適用要件が厳しく、不備によって認められない場合もあります。
利用を検討している場合は、早めに専門家に相談し、計画的に進めることをおすすめします。